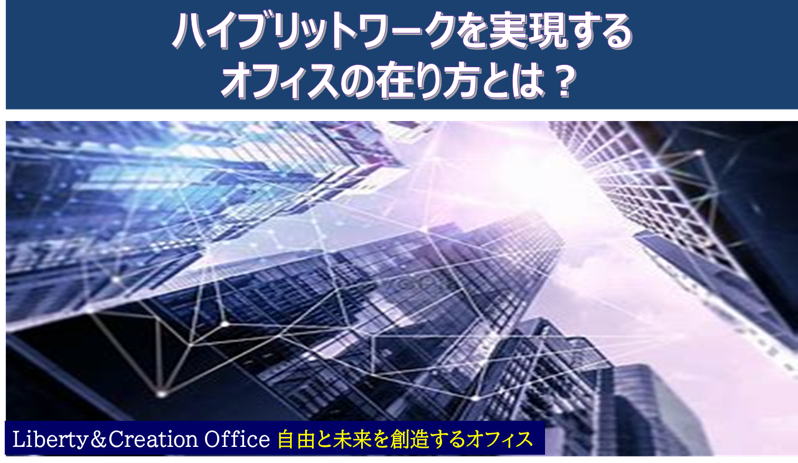サイト内検索
ソリューションコラム
- トップページ
- ソリューションコラム
- 今求められているオフィスでのコミュニケーションの形とは?重要性からメリット・デメリットまで解説
今求められているオフィスでのコミュニケーションの形とは?重要性からメリット・デメリットまで解説
2025.01.07
今日では、オフィスコミュニケーションの重要性が、より意識されるようになりました。会社内でコミュニケーションを活性化させると、部署内あるいは部署間の連携が高まり、課題解決やアイデア出しがスムーズに進み、さらには職場環境の改善につながるからです。とはいえ、なかには「オフィスでのコミュニケーションとは何?」「今までやってきた会話と何が違うの?」「メリットもあれば、デメリットもあるのでは?」と、疑問を抱いている管理者や担当者がいらっしゃるかもしれません。
そこで本記事では、オフィスコミュニケーションが必要となった背景や、コミュニケーションを活性化させるメリット・デメリット、および活性化に向けたヒントをお話しします。オフィスでのコミュニケーションを活性化させたい企業の皆様はぜひ参考にしてください。
目次
そもそもオフィスでのコミュニケーションとは?
オフィスコミュニケーションとは、会社内で取り交わされるあらゆる会話です。上司と部下、同僚同士の会話、チーム内・部署内あるいは部署を横断する会話、そして指示・報告、会議での議論、さらには雑談まで、すべてがオフィスコミュニケーションに含まれます。
オフィスコミュニケーションとプライベートでの日常的な会話の根本的な違いは、収益の増加、コスト削減、課題解決、職場の雰囲気改善、チームワークや信頼関係の向上など、オフィスコミュニケーションが企業活動と緊密に結びついている点です。
オフィスコミュニケーションとプライベートでの日常的な会話の根本的な違いは、収益の増加、コスト削減、課題解決、職場の雰囲気改善、チームワークや信頼関係の向上など、オフィスコミュニケーションが企業活動と緊密に結びついている点です。
時代に合わせて変化するオフィスでのコミュニケーション
オフィスでのコミュニケーションの形は、時代に合わせて姿を変えているといえるでしょう。ここでは、コミュニケーションの変化や、今現在求められているコミュニケーションの形を解説します。
オフィスコミュニケーションは、教育環境の変化や従業員の多国籍化などの人的な要因、SNSの発達など技術の進化により変化しています。
「教えられるのではなく、先輩の背中を見ながら育ったものだ」というようなひと昔前のやり方では、もはや人材が育たなくなってきました。
ジェネレーションギャップといえばそれまでですが、それでも企業活動を推進するためには、時代に適合したコミュニケーション方法を採用していかなければなりません。
時代に合わせたオフィスでのコミュニケーション方法の採用
オフィスコミュニケーションは、教育環境の変化や従業員の多国籍化などの人的な要因、SNSの発達など技術の進化により変化しています。
「教えられるのではなく、先輩の背中を見ながら育ったものだ」というようなひと昔前のやり方では、もはや人材が育たなくなってきました。
ジェネレーションギャップといえばそれまでですが、それでも企業活動を推進するためには、時代に適合したコミュニケーション方法を採用していかなければなりません。
業務上の課題解決の糸口となる
コミュニケーションの質や量を改善するためには、オープン化とフラット化が求められています。というのも、価値観の多様化、言語や風習の壁、さらにはSNSにおける真偽不明の情報の氾濫に対応するために、オフィスコミュニケーションが欠かせないからです。
部署間の仕切りを取り除いてオフィスをフラット化するなどして、従業員がより多くの接点を持てるように工夫するとよいでしょう。
また、部長室を廃止したり、お互いが一個人として尊重して接したりするなど、上司・部下、あるいは先輩・後輩の関係のフラット化も大切です。
部署間の仕切りを取り除いてオフィスをフラット化するなどして、従業員がより多くの接点を持てるように工夫するとよいでしょう。
また、部長室を廃止したり、お互いが一個人として尊重して接したりするなど、上司・部下、あるいは先輩・後輩の関係のフラット化も大切です。
オフィスでのコミュニケーションを活性化するメリット・デメリット
オフィスコミュニケーションを活性化するとどのようなメリットがあり、活性化することでどのようなデメリットが潜んでいるのでしょうか。
コミュニケーションを活性化した際の、メリット・デメリットをまとめてみました。
オフィスでのコミュニケーションを活性化するメリットは、生産性の向上、帰属意識や信頼関係の醸成、職場環境の改善です。
〈生産性の向上〉
従業員一人ひとりが持つ情報を考案しあうと、業務がスムーズに進んだり、あるいは新たなアイデアが生まれたりします。
また、部署間のコミュニケーションが活性することで、いわゆる部署間の見えない壁の解消や、立場の相互理解が進むことも。結果として、会社内の生産性向上につながります。
〈帰属意識や信頼関係の醸成〉
コミュニケーションが活性化すると、人間関係がより密になり、帰属意識や信頼関係が醸成されます。業務を遂行するためにチームワークを必要とする職場ほど、活発な会話が必要といえるでしょう。
会話を頻繁におこなうと、誤解や偏見が解消され従業員同士の信頼関係がより強くなります。
コミュニケーションを活性化した際の、メリット・デメリットをまとめてみました。
オフィスでのコミュニケーションを活性化するメリット
オフィスでのコミュニケーションを活性化するメリットは、生産性の向上、帰属意識や信頼関係の醸成、職場環境の改善です。
〈生産性の向上〉
従業員一人ひとりが持つ情報を考案しあうと、業務がスムーズに進んだり、あるいは新たなアイデアが生まれたりします。
また、部署間のコミュニケーションが活性することで、いわゆる部署間の見えない壁の解消や、立場の相互理解が進むことも。結果として、会社内の生産性向上につながります。
〈帰属意識や信頼関係の醸成〉
コミュニケーションが活性化すると、人間関係がより密になり、帰属意識や信頼関係が醸成されます。業務を遂行するためにチームワークを必要とする職場ほど、活発な会話が必要といえるでしょう。
会話を頻繁におこなうと、誤解や偏見が解消され従業員同士の信頼関係がより強くなります。
〈職場環境の改善〉
コミュニケーションにより気軽に相談できる職場が、より働きやすいのはいうまでもありません。もちろん、業務上の事柄だけでなく、プライベートの事柄も相談できる環境は、従業員にとって心強いものです。
コミュニケーションの活性化が。従業員の定着率の向上にも寄与するでしょう。
コミュニケーションが活性化され交換する情報量が増えると、業務上の重要な事柄や、取引先や顧客などの個人情報が漏洩するリスクが高まります。このため、情報管理や極めて重要な情報の扱い方に対する教育を強化しなければなりません。
また、昨今では誰もがSNSを通じて容易に不特定多数に情報を発信できるため、情報の取り扱いなどを定めた情報セキュリティポリシーの策定も必要です。
コミュニケーションにより気軽に相談できる職場が、より働きやすいのはいうまでもありません。もちろん、業務上の事柄だけでなく、プライベートの事柄も相談できる環境は、従業員にとって心強いものです。
コミュニケーションの活性化が。従業員の定着率の向上にも寄与するでしょう。
オフィスでのコミュニケーションを活性化するデメリット
コミュニケーションが活性化され交換する情報量が増えると、業務上の重要な事柄や、取引先や顧客などの個人情報が漏洩するリスクが高まります。このため、情報管理や極めて重要な情報の扱い方に対する教育を強化しなければなりません。
また、昨今では誰もがSNSを通じて容易に不特定多数に情報を発信できるため、情報の取り扱いなどを定めた情報セキュリティポリシーの策定も必要です。
オフィスでのコミュニケーションを活性化させるヒント
オフィスコミュニケーションを活性化させるには、ハード面およびソフト面の両面からの取り組みが欠かせません。それぞれの取り組みの概要は次のとおりです。
ハード面からの取り組みとは、コミュニケーションがはずむオフィスづくりです。取り組みや仕掛け例をご紹介します。
まず、パーティションを撤去して開放的な空間にします。
続いて、エリアマネジメントをおこない、動線を考慮して机やコピー機置き場、休憩スペースを配置しましょう。エリアマネジメントのポイントは、コミュニケーションの機会を自然と増やすために、従業員同士の接点をより多くすることです。
さらに踏み込んで、好きな場所で仕事をするフリーアドレスを導入するとよいかもしれません。
最後に、会話や交流機会を増やす仕掛けとして、コミュニケーションボードなどのツールの検討もよいでしょう。
もちろん、オフィスのスペース不足の関係で、すべてを取り組めるとはかぎりません。コミュニケーションが活性化された他社の事例を参考に、自社に見合う形で工夫するとよいでしょう。
ソフト面からの取り組みは、話す人および聞く人のコミュニケーションスキルの向上をいいます。
コミュニケーションの基本原則は、「明快であること」「相手の話にしっかり耳を傾けること」「あらかじめ話す内容を整理すること」の3点です。
限られた時間で仕事をこなし、かつ効果的にコミュニケーションを図るには、ある程度のコミュニケーションスキルの向上が必須といえるでしょう。
コミュニケーションの質を向上させるために、コミュニケーションスキルを磨くレッスンを、企業内で提供するとよいかもしれません。
ハード面からの取り組み
ハード面からの取り組みとは、コミュニケーションがはずむオフィスづくりです。取り組みや仕掛け例をご紹介します。
まず、パーティションを撤去して開放的な空間にします。
続いて、エリアマネジメントをおこない、動線を考慮して机やコピー機置き場、休憩スペースを配置しましょう。エリアマネジメントのポイントは、コミュニケーションの機会を自然と増やすために、従業員同士の接点をより多くすることです。
さらに踏み込んで、好きな場所で仕事をするフリーアドレスを導入するとよいかもしれません。
最後に、会話や交流機会を増やす仕掛けとして、コミュニケーションボードなどのツールの検討もよいでしょう。
もちろん、オフィスのスペース不足の関係で、すべてを取り組めるとはかぎりません。コミュニケーションが活性化された他社の事例を参考に、自社に見合う形で工夫するとよいでしょう。
ソフト面からの取り組み
ソフト面からの取り組みは、話す人および聞く人のコミュニケーションスキルの向上をいいます。
コミュニケーションの基本原則は、「明快であること」「相手の話にしっかり耳を傾けること」「あらかじめ話す内容を整理すること」の3点です。
限られた時間で仕事をこなし、かつ効果的にコミュニケーションを図るには、ある程度のコミュニケーションスキルの向上が必須といえるでしょう。
コミュニケーションの質を向上させるために、コミュニケーションスキルを磨くレッスンを、企業内で提供するとよいかもしれません。
まとめ
オフィスコミュニケーションは、ますます重要性が増してきたツールの一つです。
コミュニケーションの質と量を改善することで、生産性の向上や職場環境の改善などの効果がある一方で、情報管理が必要となることも。
コミュニケーションが活性化したオフィスは、ハード面であれ、ソフト面であれ、一朝一夕でできあがるものではありません。経営者と従業員が一体となって地道に取り組み、企業文化として育てていくものです。まずは、手をつけやすいところからスタートしてみてはいかがでしょうか。
コミュニケーションの質と量を改善することで、生産性の向上や職場環境の改善などの効果がある一方で、情報管理が必要となることも。
コミュニケーションが活性化したオフィスは、ハード面であれ、ソフト面であれ、一朝一夕でできあがるものではありません。経営者と従業員が一体となって地道に取り組み、企業文化として育てていくものです。まずは、手をつけやすいところからスタートしてみてはいかがでしょうか。