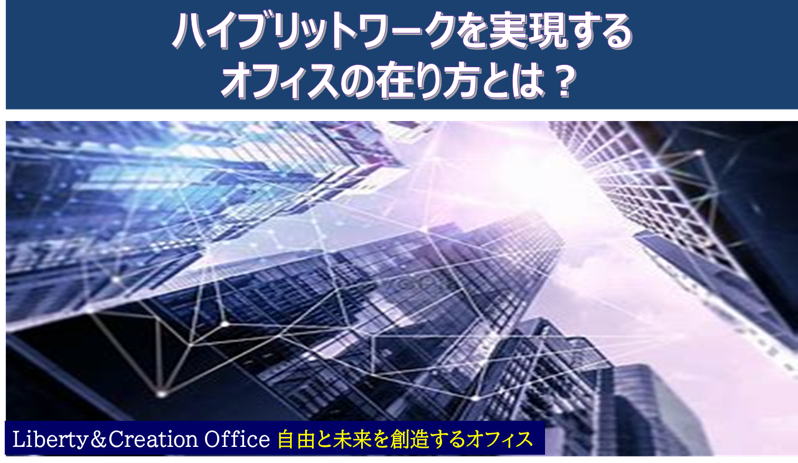サイト内検索
ソリューションコラム
- トップページ
- ソリューションコラム
- 働き方改革はどう進めるべき?企業の取り組み事例から見出す課題解決策
働き方改革はどう進めるべき?企業の取り組み事例から見出す課題解決策
2025.07.23
働き方改革は単なる制度導入ではなく、組織の在り方を見直すとともにウェルビーイング経営を目指す取り組みです。多様な価値観を尊重し、従業員の生活・健康・成長を支える職場整備は、企業の競争力を強化する上で欠かせません。
しかし、中小企業では様々な課題があり、思うように改革が進まないことも少なくありません。
本記事では、働き方改革の目的や課題を整理し、企業の実践事例から中小企業に役立つ解決策を読み解きます。
目次
働き方改革とは?その目的と社会・企業における重要性
働き方改革とは、少子高齢化や労働人口減少が進む日本において、労働力不足が故の長時間労働、多様化する働き方への課題に対応するために、政府が主導し進めている労働環境・制度の見直しです。
具体的な目的には、長時間労働の是正と健康管理、多様な人材(育児・介護中の人、高齢者など)の活用、柔軟な働き方による業務の効率化、離職防止と採用力の強化などが含まれます。
また、SDGs(持続可能な開発目標)の目標8「働きがいも経済成長」とも方向性を同じくしており、企業の社会的責任として重要視されています。
※SDGs(持続可能な開発目標)の目標8「働きがいも経済成長」について詳しくはこちらをご覧下さい。
農林水産省ホームページSDGsの目標とターゲット
具体的な目的には、長時間労働の是正と健康管理、多様な人材(育児・介護中の人、高齢者など)の活用、柔軟な働き方による業務の効率化、離職防止と採用力の強化などが含まれます。
また、SDGs(持続可能な開発目標)の目標8「働きがいも経済成長」とも方向性を同じくしており、企業の社会的責任として重要視されています。
※SDGs(持続可能な開発目標)の目標8「働きがいも経済成長」について詳しくはこちらをご覧下さい。
農林水産省ホームページSDGsの目標とターゲット
中小企業が直面する課題と“見落としがちな壁”
中小企業が働き方改革を進めるには、現場の実情に即した職場環境の見直しが重要です。制度を整えても、現場に負担や誤解があれば、改革が形骸化する恐れがあります。
例えば、「制度はあるが使いづらい」「業務の属人化でチームとしての事ができない」「コスト負担が大きい」など、現場では様々な課題が根深く残っています。このような見えにくい壁が改革の妨げになっているのです。
だからこそ、実務レベルでの課題や職場の慣習にも向き合うことが、本質的な働き方改革に必要不可欠です
例えば、「制度はあるが使いづらい」「業務の属人化でチームとしての事ができない」「コスト負担が大きい」など、現場では様々な課題が根深く残っています。このような見えにくい壁が改革の妨げになっているのです。
だからこそ、実務レベルでの課題や職場の慣習にも向き合うことが、本質的な働き方改革に必要不可欠です
【課題別】職場活性化への具体例と期待できる効果
ここからは、各課題への対策と期待できる効果を見ていきます。課題は一見共通しているように見えても、企業ごとにその背景や実情は異なります。自社の現状と照らし合わせて課題を確認してみてください。
長時間労働の是正は、最優先で改善すべき課題です。過剰な勤務時間は、従業員の健康や意欲を損ない、生産性の低下を招く恐れがあります。
業務の棚卸しや会議の削減、残業時間の数値管理などにより、業務の優先度を見極めた効率的な働き方を進めることで、勤務時間の短縮が可能です。特に、残業の事前承認制や定時退社日の導入は着手しやすく、現場の意識改革のきっかけにもなります。
労働時間を適正に保つことは、疲労の蓄積を防ぐだけでなく、生産性向上や離職防止といったプラス効果が期待されます。
1.長時間労働
長時間労働の是正は、最優先で改善すべき課題です。過剰な勤務時間は、従業員の健康や意欲を損ない、生産性の低下を招く恐れがあります。
業務の棚卸しや会議の削減、残業時間の数値管理などにより、業務の優先度を見極めた効率的な働き方を進めることで、勤務時間の短縮が可能です。特に、残業の事前承認制や定時退社日の導入は着手しやすく、現場の意識改革のきっかけにもなります。
労働時間を適正に保つことは、疲労の蓄積を防ぐだけでなく、生産性向上や離職防止といったプラス効果が期待されます。
2.柔軟な働き方の欠如
柔軟な働き方が浸透しない職場は、ワークライフバランスが乱れ離職率が高くなりがちです。画一的な勤務形態では、従業員個々の生活に合った働き方が難しいためです。
制度の全面導入が難しい場合には、一部の部署や職種で段階的に始めるのが現実的です。例として、週1回のリモート勤務やフレックスタイム制の試行があります。スケジュール管理ツールやチャットアプリを使えば、業務連絡も円滑に進められます。
柔軟な働き方が可能になれば、育児や介護との両立がしやすくなり、従業員の定着率やエンゲージメントの向上につながります。
3.人材活用の停滞
多様な人材の活用は、企業の競争力強化に不可欠です。多様性を尊重しない環境では、アイデアの幅が狭まり、変化への対応力が低下しやすくなります。
具体的には、障がい者や高齢者に適した業務をチーム単位で編成し、無理のない範囲で戦力として活躍できる体制を整えます。また、ダイバーシティ推進研修の実施や管理職の意識変革も効果的です。
これらの施策を通じて、様々な視点からの発想が促され、組織の活性化を図れます。
4.属人化
属人化した業務は、担当者の不在時に業務が止まるなど、大きなリスクを孕んでいます。
その解決策として有効なのが、業務プロセスの可視化とマニュアル整備です。マニュアル作成や情報共有ツール(チャット・クラウド・社内SNSなど)の導入により、複数人で対応可能な体制を構築できるだけでなく無駄な業務も見えてきます。
このような対応は、急な欠勤時にも業務が滞らず、不測の事態でも業務が継続できる仕組みとして、一定の成果が見込めます。
5.情報共有不足
従業員相互の情報共有が不十分な場合、意思決定の遅延や業務の重複といった問題が生じます。
これらを回避するためには、定期的なミーティングや共通の情報共有ツールの導入に加え、オフィスレイアウトの見直しで日々のコミュニケーション改善に取り組むとともに全社横断的なプロジェクト編成も効果的です。
自社に適した工夫を行うことで、部署間の連携が活性化し、業務の重複や行き違いの減少が期待できます。
働き方改革の成功事例から見出す中小企業のアプローチ策
以下に紹介する企業の事例は業種や規模は異なりますが、多くが共通する課題に対応し、複数の問題を同時に解決しています。
実践施策を検討する際は、自社の課題と明確な目標をたてることで全体像をしっかり把握することが重要です。その上で段階的に導入することでスムーズな移行が可能です。
近年業績好調なA社では、テレワーク制度の本格導入後も、フレックス勤務の拡大や在宅勤務の費用補助、育児や介護を考慮した在宅勤務の導入、地方移住を伴う勤務やワーケーションの推進など、多様な施策を展開しています。
ICT環境の整備も進め、どこからでも安全に業務ができる体制も構築。テレワーク率は約80%を維持し、通勤時間削減や健康状態の改善にもつながりました。
在宅勤務や遠隔勤務の拡充も、ワークライフバランスの向上を後押ししています。
実践施策を検討する際は、自社の課題と明確な目標をたてることで全体像をしっかり把握することが重要です。その上で段階的に導入することでスムーズな移行が可能です。
【事例① A社(ITサービス)】ICT×テレワークでプライベート両立を実現
近年業績好調なA社では、テレワーク制度の本格導入後も、フレックス勤務の拡大や在宅勤務の費用補助、育児や介護を考慮した在宅勤務の導入、地方移住を伴う勤務やワーケーションの推進など、多様な施策を展開しています。
ICT環境の整備も進め、どこからでも安全に業務ができる体制も構築。テレワーク率は約80%を維持し、通勤時間削減や健康状態の改善にもつながりました。
在宅勤務や遠隔勤務の拡充も、ワークライフバランスの向上を後押ししています。
【事例②B社(建設)】女性活躍を起点に進めたSDGs視点のオフィス改革とフリーアドレス
近年優秀な社員を多く採用しているB社では、女性従業員の入社をきっかけに、社内に根強く残っていた慣習の見直しを図り、来客対応や清掃業務、制服など、制度面からも男女平等の環境づくりを推進しました。
その結果、女性従業員から自発的な声が上がり、フリーアドレスを導入。従業員間の交流が活発化し、意見交換や業務連携の質が向上しました。
女性を含む多様な人材が主体的に働ける風土が根付きつつあります。
近年若い社員が年々増えているC社では、従業員が家族と過ごす時間を確保できるよう、年次有給休暇付与制度を段階的に見直しました。
夏季休暇の一斉取得日数を拡大し、長期休暇と組み合わせやすい仕組みを整備。加えて、入社時における休暇日数も付与することで、休暇取得の計画性と心理的ハードルを下げました。
社内カレンダーでの取得日周知や部署ごとのフォロー体制も整えた結果、有給休暇取得率は約90%に上昇し、従業員の生活の質(QOL)も向上しました。
その結果、女性従業員から自発的な声が上がり、フリーアドレスを導入。従業員間の交流が活発化し、意見交換や業務連携の質が向上しました。
女性を含む多様な人材が主体的に働ける風土が根付きつつあります。
【事例③ C社(電子部品製造)】有休取得がQOLとプライベート充実を後押し
近年若い社員が年々増えているC社では、従業員が家族と過ごす時間を確保できるよう、年次有給休暇付与制度を段階的に見直しました。
夏季休暇の一斉取得日数を拡大し、長期休暇と組み合わせやすい仕組みを整備。加えて、入社時における休暇日数も付与することで、休暇取得の計画性と心理的ハードルを下げました。
社内カレンダーでの取得日周知や部署ごとのフォロー体制も整えた結果、有給休暇取得率は約90%に上昇し、従業員の生活の質(QOL)も向上しました。
【事例④ D社(サービス)】ICTで現場力を強化し、生産性と顧客満足を向上
生産性が劇的に向上したD社では、生産部門・販売部門の両方にICTを導入することで現場力を強化しました。
工場では、新型機器の導入や製造プロセスの見える化(マニュアル作成)により、新入社員でも短期間で即戦力となる体制を整備。これにより、業務の属人化が解消され、品質のばらつきも大幅に減少しました。
時間あたりの生産量が約2倍に向上し、品質改善や販促強化により売上だけでなく顧客満足度も上がっています。
【事例⑤ E社(製造)】健康支援とQOL向上を軸にしたSDGs対応
生産性と働きやすさのバランスを目指しているE社では、従業員のエンゲージメント向上と業務改善を目的に、外部講師を招き研修を定期開催しました。さらに、禁煙手当や栄養士によるセミナーの実施、社内イベントで従業員同士の交流を深めるなど、働きがいと健康を両立する職場づくりが進んでいます。
その結果、育児休業取得率100%、所定外労働の抑制と受注増への対応を両立し、生産性と働きやすさのバランスを実現しています。
課題の可視化から始める!中小企業の取り組み促進プラン
働き方改革に取り組むには、最初に現場の状況を正確に把握することが不可欠です。実態をつかまずに施策を決めると、効果がでないだけでなく現場から大きな反発が起こりかねません。
具体的には、従業員アンケートなどの実態調査による業務時間のデータ分析、生産性向上へ向けた改善要望事項の整理把握などがあります。これらの情報をもとに、無理なく取り組める内容を設定し、小規模な試行から始める流れが適しています。
業務プロセスや働き方改革を目指した改善は一朝一夕にはいきません。段階的な見直しへの対応だけでなくトライアンドエラーを繰り返し、形式より実態を重視した継続的な改善を促す工夫が必要です。
具体的には、従業員アンケートなどの実態調査による業務時間のデータ分析、生産性向上へ向けた改善要望事項の整理把握などがあります。これらの情報をもとに、無理なく取り組める内容を設定し、小規模な試行から始める流れが適しています。
業務プロセスや働き方改革を目指した改善は一朝一夕にはいきません。段階的な見直しへの対応だけでなくトライアンドエラーを繰り返し、形式より実態を重視した継続的な改善を促す工夫が必要です。
【まとめ】オフィスとICTで描く中小企業の働き方改革ロードマップ
中小企業が働き方改革を進めるには、現場の声を聞き、自社に必要な変化を見極めることが重要です。長時間労働や属人化、情報共有不足といった課題は、制度やICTを導入するだけでは解消できません。
事例からも、ICT活用・オフィス環境の見直し・意識改革を組み合わせることが、働き方の改善に効果的であることが分かります。
まずは課題を可視化し、現場との対話を通じて進むべき方向を明らかにすることが、これからの職場づくりには欠かせません。
事例からも、ICT活用・オフィス環境の見直し・意識改革を組み合わせることが、働き方の改善に効果的であることが分かります。
まずは課題を可視化し、現場との対話を通じて進むべき方向を明らかにすることが、これからの職場づくりには欠かせません。