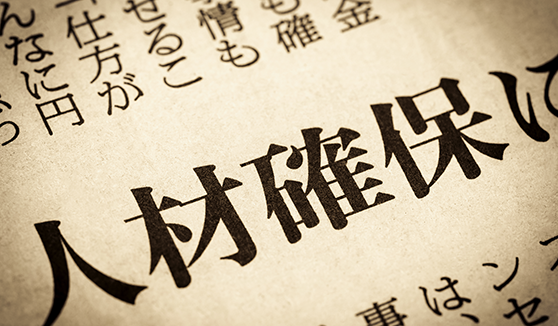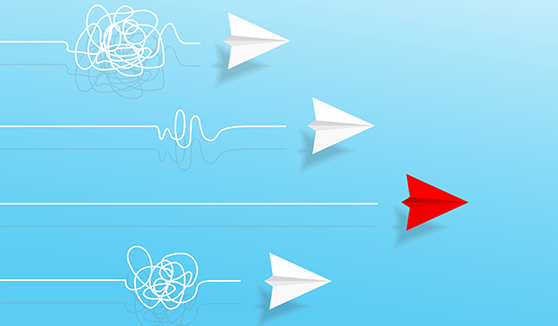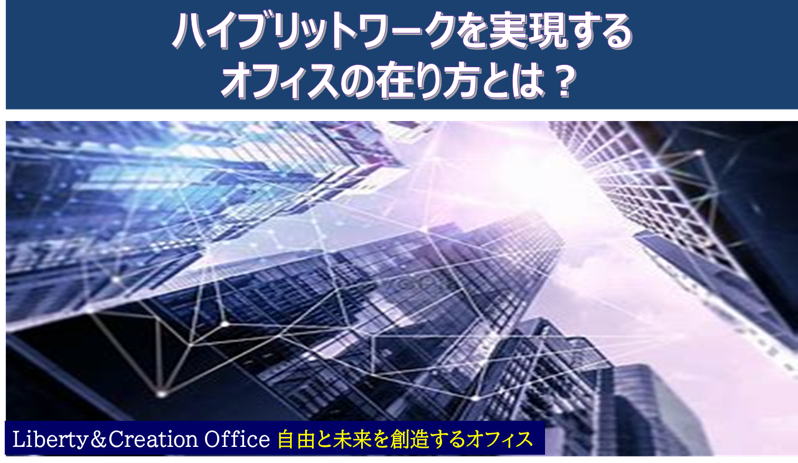サイト内検索
ソリューションコラム
- トップページ
- ソリューションコラム
- 【2025年最新】中小企業の働き方改革実践方法
5つのステップと効果的な取り組み方
【2025年最新】中小企業の働き方改革実践方法
5つのステップと効果的な取り組み方
2025.10.31
長時間労働の是正や柔軟な勤務制度の重要性が問われている昨今、働き方改革に取り組む企業も増えています。とはいえ、実際に働き方改革が成功する企業もいれば、失敗に終わってしまう企業がいることも事実です。
本記事では、実際の具体例を紹介しながら、それぞれの企業がどのような工夫や課題を抱えていたのか詳しく解説します。働き方改革を形だけで終わらせないためのコツにも触れていますので、導入前に押さえておくべきポイントとしてご参考ください。
目次
はじめに|なぜ中小企業に働き方改革が必要なのか
「働き方改革って大企業だけの話でしょう?」そう考えている中小企業の経営者の方も多いのではないでしょうか。しかし中小企業こそ働き方改革に真剣に取り組まなければならない時代に突入しています。
厚生労働省の調査によると、日本の労働力人口は2030年までに約800万人減少すると予測されており、特に従業員100から200人規模の中小企業では、人材確保がこれまで以上に困難になることが確実視されています。実際、2024年の「人手不足倒産」は前年比約40%増加という深刻な状況です。
厚生労働省の調査によると、日本の労働力人口は2030年までに約800万人減少すると予測されており、特に従業員100から200人規模の中小企業では、人材確保がこれまで以上に困難になることが確実視されています。実際、2024年の「人手不足倒産」は前年比約40%増加という深刻な状況です。
一方で、求職者の働き方に対する意識は近年大きく変化しています。転職理由の上位には「労働時間・休日」「職場環境」が挙がっており、給与よりも働きやすさを重視する傾向が強まっているのです。つまり、働き方改革に取り組まない企業は、優秀な人材に選ばれない企業となってしまうというわけです。
本記事では、限られたリソースの中で効果的に働き方改革を推進し、人材確保と生産性向上を同時に実現する具体的な方法を5つのステップで解説します。
本記事では、限られたリソースの中で効果的に働き方改革を推進し、人材確保と生産性向上を同時に実現する具体的な方法を5つのステップで解説します。
中小企業における働き方改革の重要性と目的
働き方改革は、中小企業にとって労働生産性の向上と従業員のQOL向上を同時に実現する重要な経営戦略です。労働人口の減少が加速する現在、中小企業では人材の確保と定着が事業継続のキーとなります。
働き方改革とは「働く人がそれぞれの事情に応じて多様な働き方を選択できる社会を実現するための取り組み」。大企業が制度改革を進める中で、中小企業がこの取り組みを怠れば、人材採用や定着で不利な立場に立たされ、採用難や離職率の上昇に直結することは明らかです。
さらに、限られた人材で生産性を維持するためには、従業員一人ひとりが働きやすい職場環境を整備することが欠かせません。働き方改革の目的は、単なる労働条件の改善だけでなく、企業の持続的な成長を支える基盤づくりです。加えて、国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の「働きがいも経済成長も」に直結しており、社会的な意義も大きいといえます。
働き方改革とは「働く人がそれぞれの事情に応じて多様な働き方を選択できる社会を実現するための取り組み」。大企業が制度改革を進める中で、中小企業がこの取り組みを怠れば、人材採用や定着で不利な立場に立たされ、採用難や離職率の上昇に直結することは明らかです。
さらに、限られた人材で生産性を維持するためには、従業員一人ひとりが働きやすい職場環境を整備することが欠かせません。働き方改革の目的は、単なる労働条件の改善だけでなく、企業の持続的な成長を支える基盤づくりです。加えて、国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の「働きがいも経済成長も」に直結しており、社会的な意義も大きいといえます。
2025年法改正動向と中小企業への影響
2025年からは働き方改革に関する重要な法改正が段階的に施行されます。育児・介護休業法の改正により、子どもの看護休暇の拡充や残業免除対象の拡大、テレワークの努力義務化などが導入され、企業には子育てや介護と仕事を両立できる職場環境づくりが一層求められるようになります。
※働き方改革に関する重要な法改正について詳しくはこちらをご覧下さい。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
※働き方改革に関する重要な法改正について詳しくはこちらをご覧下さい。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
これらの改正は、企業の規模に関わらず適用されます。中小企業においても例外はなく、法的要件を満たすだけでなく、変化を先取りして競争優位性につなげる姿勢が重要です。特に今回の改正では、単なる制度追加ではなく企業文化や働き方そのものの再設計を促す内容となっているため、積極的な対応が必要となるのです。
働き方改革で得られる効果と企業のメリット
中小企業が働き方改革に取り組むことで得られる効果は多くあります。
まず、労働生産性の向上です。労働時間の適正化により従業員の集中力が維持され、作業効率の改善やミスの削減につながります。
そして、人材の定着率改善です。働きやすい環境を整えることで離職率を下げ、優秀な人材の流出を防ぐことができます。加えて企業イメージが向上し、採用活動における求職者からの評価も高くなります。
最後に、職場活性化の効果です。多様な働き方を認めることで従業員のモチベーションが高くなり、職場全体の雰囲気が改善されます。
これらの効果は一度の取り組みで完結するものではありません。継続的な努力により定着させることで、企業の成長力につながっていきます。
まず、労働生産性の向上です。労働時間の適正化により従業員の集中力が維持され、作業効率の改善やミスの削減につながります。
そして、人材の定着率改善です。働きやすい環境を整えることで離職率を下げ、優秀な人材の流出を防ぐことができます。加えて企業イメージが向上し、採用活動における求職者からの評価も高くなります。
最後に、職場活性化の効果です。多様な働き方を認めることで従業員のモチベーションが高くなり、職場全体の雰囲気が改善されます。
これらの効果は一度の取り組みで完結するものではありません。継続的な努力により定着させることで、企業の成長力につながっていきます。
段階的に進める働き方改革の5ステップ
中小企業が働き方改革を成功させるためには、段階的かつ戦略的なアプローチが必要です。
ステップ①は、現状分析と目標設定です。労働時間の実態を把握するため、タイムカードやPCログを活用して部署ごとの特徴や隠れ残業を洗い出します。同時に従業員アンケートや面談を通じて現場の声を収集し、改善すべき課題を明確にします。目標設定では「残業時間を月20時間以内」「有給取得率70%以上」など具体的で測定可能な指標を設定することが重要です。
ステップ②は、経営層のコミットメントと推進体制の構築です。制度変更を現場任せにしては定着は難しくなります。経営層自らが働き方改革の意義を全社員に伝え、推進委員会を設置して各部署から代表者を選出します。定期的な進捗確認と課題解決を行う体制を整えることで、取り組みを持続させる基盤となります。
ステップ③は、制度整備と環境改善です。フレックスタイム制や時差出勤制度の導入に加え、2025年法改正を見据えたテレワーク制度の導入を検討する必要があります。有給休暇の取得促進では、計画的付与制度や記念日休暇の仕組みを整えることが有効です。管理職が率先して休暇を取得することで、「休んでも良い」という文化を職場に根付かせることができます。
ステップ①
ステップ①は、現状分析と目標設定です。労働時間の実態を把握するため、タイムカードやPCログを活用して部署ごとの特徴や隠れ残業を洗い出します。同時に従業員アンケートや面談を通じて現場の声を収集し、改善すべき課題を明確にします。目標設定では「残業時間を月20時間以内」「有給取得率70%以上」など具体的で測定可能な指標を設定することが重要です。
ステップ②
ステップ②は、経営層のコミットメントと推進体制の構築です。制度変更を現場任せにしては定着は難しくなります。経営層自らが働き方改革の意義を全社員に伝え、推進委員会を設置して各部署から代表者を選出します。定期的な進捗確認と課題解決を行う体制を整えることで、取り組みを持続させる基盤となります。
ステップ③
ステップ③は、制度整備と環境改善です。フレックスタイム制や時差出勤制度の導入に加え、2025年法改正を見据えたテレワーク制度の導入を検討する必要があります。有給休暇の取得促進では、計画的付与制度や記念日休暇の仕組みを整えることが有効です。管理職が率先して休暇を取得することで、「休んでも良い」という文化を職場に根付かせることができます。
ステップ④
ステップ④は、デジタル化による業務効率化です。クラウド型の業務管理システムを導入することで、情報共有と進捗管理がスムーズになり、時間や場所にとらわれない働き方が可能となります。オンライン会議やチャットツールを活用すれば、移動時間を削減し迅速な意思決定が可能になります。デジタル化は効率化にとどまらず、柔軟な働き方を支える基盤となるのです。
ステップ⑤
ステップ⑤は、継続的な改善と効果測定です。設定した目標の達成状況を月次あるいは四半期ごとに確認し、労働時間や有給取得率などの定量データに加えて従業員の満足度や職場の雰囲気を評価します。現場の声を定期的に吸い上げることで新たな課題を早期に発見し、制度の見直しや追加施策を迅速に行うことができます。
働き方改革導入時の課題と解決策
中小企業が働き方改革を導入する際に直面する最大の課題は、制度と現場の業務実態とのかい離です。理想的な制度を設計しても、現場に合わなければ形骸化し、効果を発揮できません。導入前には現場ヒアリングを行い、一部部署で試行運用をしてから全社展開することが有効です。
管理職のマネジメント力不足が問題になるケースもあります。時間管理から成果管理へと転換するためには、明確な目標設定と公平な評価制度が欠かせません。管理職研修や評価制度の見直しを通じて、新しい働き方に対応できるマネジメント力を高めることが管理層に求められます。
さらに、生産性維持への配慮も重要です。労働時間削減を進めるにあたっては、業務プロセスの見直しやデジタル化、従業員のスキル向上を同時に進める必要があります。これらを実現することで、労働時間の短縮と業務品質の維持の両立が可能となるのです。
働き方改革を成功させるには、制度導入に加えて業務効率化の工夫も欠かせません。
【あわせて読みたい】すぐ実践できるペーパーレス化の方法を紹介! メリットや注意点、進まない原因なども解説
管理職のマネジメント力不足が問題になるケースもあります。時間管理から成果管理へと転換するためには、明確な目標設定と公平な評価制度が欠かせません。管理職研修や評価制度の見直しを通じて、新しい働き方に対応できるマネジメント力を高めることが管理層に求められます。
さらに、生産性維持への配慮も重要です。労働時間削減を進めるにあたっては、業務プロセスの見直しやデジタル化、従業員のスキル向上を同時に進める必要があります。これらを実現することで、労働時間の短縮と業務品質の維持の両立が可能となるのです。
働き方改革を成功させるには、制度導入に加えて業務効率化の工夫も欠かせません。
【あわせて読みたい】すぐ実践できるペーパーレス化の方法を紹介! メリットや注意点、進まない原因なども解説
中小企業の成功事例から学ぶ
ある情報通信企業では、2017年度に月平均28時間だった残業時間を2021年度には20時間まで削減。さらに、オンライン研修の導入により地方拠点の従業員も大都市圏と同じ教育機会を得られるようになり、労働時間削減と従業員満足度の向上を同時に実現しました。
また、ある電気工事会社では経営トップが率先して長時間労働の是正に取り組んだことで社員の意識改革が進み、労働環境改善と企業活性化を両立させています。
いずれの事例も、経営層のリーダーシップと現場に即した実践が成功の要因となっています。
さらに具体的な成功・失敗事例や課題解決のヒントについては、以下の記事もご覧ください。
【あわせて読みたい】働き方改革の成功事例・失敗事例を紹介!成功させるコツも解説
【あわせて読みたい】働き方改革はどう進めるべき?企業の取り組み事例から見出す課題解決策
また、ある電気工事会社では経営トップが率先して長時間労働の是正に取り組んだことで社員の意識改革が進み、労働環境改善と企業活性化を両立させています。
いずれの事例も、経営層のリーダーシップと現場に即した実践が成功の要因となっています。
さらに具体的な成功・失敗事例や課題解決のヒントについては、以下の記事もご覧ください。
【あわせて読みたい】働き方改革の成功事例・失敗事例を紹介!成功させるコツも解説
【あわせて読みたい】働き方改革はどう進めるべき?企業の取り組み事例から見出す課題解決策
まとめ|中小企業が成功する働き方改革の実践
働き方改革は、大企業・中小企業問わず多くの企業が取り組むべきテーマです。成功させるには、ただ制度を導入するだけでなく、現場の実態に即した工夫が欠かせません。
まずは同業他社や同程度の規模感を持つ企業の成功事例に着目しながら、自社に合う取り組みを探していきましょう。
まずは同業他社や同程度の規模感を持つ企業の成功事例に着目しながら、自社に合う取り組みを探していきましょう。